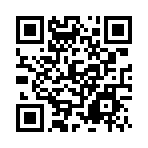2008年01月31日
『五行歌の事典』 鑑賞交換日記 (その6)
《 鑑賞作品・その6 》

空が青いと云って
ひと休み
海がきれいと云っては
ひと休み
年寄二人の初詣
松下 親
【作者紹介】 松下 親さんは、この作品を創られたとき、なんと、九十一歳の
おばあさんだったそうです。
※上の写真をクリックすると、写真が拡大表示されます。
*******************************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
◇写真の出展
「知念岬公園へ降りる道より」 ~壁紙ご提供サイト~
http://k-kabegami.sakura.ne.jp/chinenmisaki/3.html
*******************************

空が青いと云って
ひと休み
海がきれいと云っては
ひと休み
年寄二人の初詣
松下 親
【作者紹介】 松下 親さんは、この作品を創られたとき、なんと、九十一歳の
おばあさんだったそうです。
※上の写真をクリックすると、写真が拡大表示されます。
*******************************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
◇写真の出展
「知念岬公園へ降りる道より」 ~壁紙ご提供サイト~
http://k-kabegami.sakura.ne.jp/chinenmisaki/3.html
*******************************
2008年01月30日
『五行歌の事典』 鑑賞交換日記 (その5)
《 鑑賞作品・その5 》
流れの軌跡を
岩に遺し
川は
みえない水で
満ちている
水源 純
*******************************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
*******************************
流れの軌跡を
岩に遺し
川は
みえない水で
満ちている
水源 純
*******************************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
*******************************
2008年01月28日
『五行歌の事典』 鑑賞交換日記 (その4)
《 鑑賞作品・その4 》
からだは
土
わたくしという
花が
咲ききる迄
寺本一川
*******************************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
*******************************
からだは
土
わたくしという
花が
咲ききる迄
寺本一川
*******************************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
*******************************
2008年01月26日
『五行歌の事典』 鑑賞交換日記 (その3)
《 鑑賞作品・その3 》
北風のなかを
郵便屋がきた
手紙も
ぴんと
つめたい
李 陽子
*******************************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
*******************************
北風のなかを
郵便屋がきた
手紙も
ぴんと
つめたい
李 陽子
*******************************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
*******************************
2008年01月25日
今日の読売新聞・静岡版に!
みなさん、ホットニュースです。
今日の読売新聞・静岡版の『よみうり 五行歌』欄に東部五行歌会から
2名の方が入選され、うち1名の方は、な、なんと特選です。
☆
[注] ( )内の文字は、原文の“ルビ”を示しています
【特選】
「顔じゃない だから」
妻は笑って言う
「ここまで来れた」
俺の癇癪(かんしゃく)
もう 破裂寸前
函南町 渡辺一三夫
《講評》 ~三好叙子先生~ (*1)
五行歌は一人ひとりの呼吸が生きる詩型。特選は、間(あい)の手の
ような2行目といい、なかでも個性的な呼吸の歌である。日常のやりとり
も窺(うかが)え、このご夫婦、絶妙のコンビとみた。
【入選】
犬をなぐった娘に
声を荒らげる
私は
犬にも娘にも
手をあげたことがない
沼津 木綿(ゆう)
《講評》
木綿さんは、思いがけない娘の行為に衝撃を受ける。
天性の優しさか、自分を律してきたのか。「犬にも娘にも」
が印象的。
☆
渡辺一三夫さん、木綿さん、本当におめでとうございました。
※ (*1) 五行歌の会本部・副主宰
※『よみうり 五行歌』は、毎週金曜日、読売新聞・静岡版に掲載されています。
今日の読売新聞・静岡版の『よみうり 五行歌』欄に東部五行歌会から
2名の方が入選され、うち1名の方は、な、なんと特選です。
☆
[注] ( )内の文字は、原文の“ルビ”を示しています
【特選】
「顔じゃない だから」
妻は笑って言う
「ここまで来れた」
俺の癇癪(かんしゃく)
もう 破裂寸前
函南町 渡辺一三夫
《講評》 ~三好叙子先生~ (*1)
五行歌は一人ひとりの呼吸が生きる詩型。特選は、間(あい)の手の
ような2行目といい、なかでも個性的な呼吸の歌である。日常のやりとり
も窺(うかが)え、このご夫婦、絶妙のコンビとみた。
【入選】
犬をなぐった娘に
声を荒らげる
私は
犬にも娘にも
手をあげたことがない
沼津 木綿(ゆう)
《講評》
木綿さんは、思いがけない娘の行為に衝撃を受ける。
天性の優しさか、自分を律してきたのか。「犬にも娘にも」
が印象的。
☆
渡辺一三夫さん、木綿さん、本当におめでとうございました。
※ (*1) 五行歌の会本部・副主宰
※『よみうり 五行歌』は、毎週金曜日、読売新聞・静岡版に掲載されています。
2008年01月25日
『五行歌の事典』 鑑賞交換日記 (その2)
《 鑑賞作品・その2 》
自販機の
光の
中に
雪が
降る
小原淳子
*******************************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
*******************************
自販機の
光の
中に
雪が
降る
小原淳子
*******************************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
*******************************
Posted by 東部五行歌 at
08:39
│Comments(2)
2008年01月24日
『五行歌の事典』 鑑賞交換日記 (その1)
◆はじめに
五行歌づくりの楽しさは、まず「作ってみる」ことから始まりますが、と同時に、ひとの作品に接して、それをじっくりと味わってみる、つまり、「鑑賞してみる」ということも大切なことです。
全国各地で行われている五行歌会の楽しさは、この「作る楽しみ」と「人の作品を互いに鑑賞し合い、共感し合える喜び」とが同時に味わえるからではないでしょうか。
五行歌の「作る楽しさ」と「鑑賞する楽しさ」、この二つは自転車の両輪のようなもので、どちらが欠けても、それは自転車とは言えないくらい大切なものです。そればかりか、これら二つの関係は相互補完の関係にあると思います。とりわけ、ひとの作品に数多く接して鑑賞眼を高めていくことが、五行歌を作るうえで、大きな力となることは間違いないようです。
そこで、今回は、草壁焔太編『五行歌の事典』(東京堂出版)に掲載されている作品の中から一日一首ずつ取り上げていきますので、みなさんが感じたことを「ひとくちコメント」として載せ合ってみませんか。
五行歌の鑑賞は、十人の読み手がいれば十通りの解釈や感想があると言われています。
このように鑑賞しなければいけない・・などというものはありません。みなさんが、今日まで生きてきた道が違えば、その作品に対する感じ方も違っていて当然だからです。
さぁ、みなさんの感性に従った、自由な感想を、短くて結構ですので書き記してみましょう。
*************** **************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
◇作者名について
敬称は省略させていただきました
*****************************
《 鑑賞作品・その1 》
五〇すぎても
ケンちゃんと
呼ぶ
古里はいつも
少年時代
船津健治
五行歌づくりの楽しさは、まず「作ってみる」ことから始まりますが、と同時に、ひとの作品に接して、それをじっくりと味わってみる、つまり、「鑑賞してみる」ということも大切なことです。
全国各地で行われている五行歌会の楽しさは、この「作る楽しみ」と「人の作品を互いに鑑賞し合い、共感し合える喜び」とが同時に味わえるからではないでしょうか。
五行歌の「作る楽しさ」と「鑑賞する楽しさ」、この二つは自転車の両輪のようなもので、どちらが欠けても、それは自転車とは言えないくらい大切なものです。そればかりか、これら二つの関係は相互補完の関係にあると思います。とりわけ、ひとの作品に数多く接して鑑賞眼を高めていくことが、五行歌を作るうえで、大きな力となることは間違いないようです。
そこで、今回は、草壁焔太編『五行歌の事典』(東京堂出版)に掲載されている作品の中から一日一首ずつ取り上げていきますので、みなさんが感じたことを「ひとくちコメント」として載せ合ってみませんか。
五行歌の鑑賞は、十人の読み手がいれば十通りの解釈や感想があると言われています。
このように鑑賞しなければいけない・・などというものはありません。みなさんが、今日まで生きてきた道が違えば、その作品に対する感じ方も違っていて当然だからです。
さぁ、みなさんの感性に従った、自由な感想を、短くて結構ですので書き記してみましょう。
*************** **************
◇作品の出典
草壁焔太編 『五行歌の事典』(東京堂出版)
http://www.tokyodoshuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-490-10579-7
◇作者名について
敬称は省略させていただきました
*****************************
《 鑑賞作品・その1 》
五〇すぎても
ケンちゃんと
呼ぶ
古里はいつも
少年時代
船津健治
2008年01月23日
2008年01月22日
あなたも「静岡東部五行歌会」に参加してみませんか?
◆「静岡東部五行歌会」へのご案内
昨年5月に誕生した静岡東部五行歌会ですが、毎月第2土曜日の午後、沼津駅前のパレットで定例歌会を催し、みんなで、お互いの作品を鑑賞し合ったり、歌評や感想を述べ合ったりしています。
みなさんも、この新しい短詩形文芸である五行歌に挑戦し、感受性に富んだ潤いのある生活を送ってみませんか?
《2月歌会のご案内》
1.日 時 2月9日(土) 1時半 ~ 5時
2.場 所 沼津市・パレット3階・Eルーム
(沼津駅南口より徒歩1分)
3.参加費 1,000円/回
※初めての方は「ご見学」ということで無料です。
☆当歌会について、詳しくお知りになりたい方は下記へお電話ください。
静岡東部五行歌会・玉井 武(TEL:090-2570-6485)
昨年5月に誕生した静岡東部五行歌会ですが、毎月第2土曜日の午後、沼津駅前のパレットで定例歌会を催し、みんなで、お互いの作品を鑑賞し合ったり、歌評や感想を述べ合ったりしています。
みなさんも、この新しい短詩形文芸である五行歌に挑戦し、感受性に富んだ潤いのある生活を送ってみませんか?
《2月歌会のご案内》
1.日 時 2月9日(土) 1時半 ~ 5時
2.場 所 沼津市・パレット3階・Eルーム
(沼津駅南口より徒歩1分)
3.参加費 1,000円/回
※初めての方は「ご見学」ということで無料です。
☆当歌会について、詳しくお知りになりたい方は下記へお電話ください。
静岡東部五行歌会・玉井 武(TEL:090-2570-6485)
2008年01月22日
「五行歌」と「五行歌の会」について
◆五行歌とは?
五行歌は自分の思いや情感を音数にとらわれないで五行に綴るという新しいかたちの短詩形文芸で誰にでも作れます。あなたもぜひ、五行歌をつくってみませんか?
◆五行歌の会について
草壁焔太主宰のご尽力により1994年4月に産声をあげた「五行歌の会」ですが、その活動の成果は目覚しく、いまでは、全国の歌会数150余、会員数は800人、歌会参加者数は
4000人を超えるに至っています。また、五行歌を総合学習等に採り入れている小・中学校の数は120校を越えています。
◇「五行歌の会」のホームページ: http://5gyohka.com/
◆《国民文化祭・しずおか2009》の五行歌部門を清水町で開催!
2009年10月に開かれる『国民文化祭・しずおか2009』の五行歌部門が駿東郡清水町の企画事業となり、同町では五行歌講座や子どもさん向けのミニミニスクールなど、町をあげてその準備に取り組んでいます。また、このとき「第19回・五行歌の会 全国大会」も同時に開催されます。
◇ NPO法人・清水町文化協会のホームページ:
http://www4.tokai.or.jp/sbunkyo/E10.htm
五行歌は自分の思いや情感を音数にとらわれないで五行に綴るという新しいかたちの短詩形文芸で誰にでも作れます。あなたもぜひ、五行歌をつくってみませんか?
◆五行歌の会について
草壁焔太主宰のご尽力により1994年4月に産声をあげた「五行歌の会」ですが、その活動の成果は目覚しく、いまでは、全国の歌会数150余、会員数は800人、歌会参加者数は
4000人を超えるに至っています。また、五行歌を総合学習等に採り入れている小・中学校の数は120校を越えています。
◇「五行歌の会」のホームページ: http://5gyohka.com/
◆《国民文化祭・しずおか2009》の五行歌部門を清水町で開催!
2009年10月に開かれる『国民文化祭・しずおか2009』の五行歌部門が駿東郡清水町の企画事業となり、同町では五行歌講座や子どもさん向けのミニミニスクールなど、町をあげてその準備に取り組んでいます。また、このとき「第19回・五行歌の会 全国大会」も同時に開催されます。
◇ NPO法人・清水町文化協会のホームページ:
http://www4.tokai.or.jp/sbunkyo/E10.htm
2008年01月22日
ごあいさつ
みなさん、こんにちは。
私、静岡東部五行歌会の世話人をやらせていただいている玉井たけしと申します。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
このだび、katochanさんのお骨折りにより「静岡東部五行歌会の公式ブログ」が船出しました。
◆当公式ブログの目的
このブログの目的は次の二つだと思います。
1.静岡県東部地方の方々に、五行歌の良さや楽しさを広く知っていただくこと。
2.東部五行歌会の参加者や五行歌に関心をお持ちの方々同士の親睦を深め合うこと。
上記の目的を達成するためには、お互いに五行歌作品を投稿し合ったり、鑑賞コメントを述べ
合ったりすることも必要かもしれません。いずれにしても、楽しく、ホカホカと湯気の立つような
ブログにしていけたら ・・・・ と願っております。
オット、その前に「五行歌っていったいなあに?」という声が聞こえてきそうですね。
それでは、とりあえず、3首ばかりご紹介を・・。
☆
看護婦さんに
笑いかける
私の赤ちゃん
今からちっくん
されるんだよ
陣内洋子
桜の下を
帰ってきたのね
花びら一枚
傘に
のせて
森本いく子
町会の
役員
六十二才で
若手
使い走り
窪谷 登
みなさん、いかがですか?
私、静岡東部五行歌会の世話人をやらせていただいている玉井たけしと申します。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
このだび、katochanさんのお骨折りにより「静岡東部五行歌会の公式ブログ」が船出しました。
◆当公式ブログの目的
このブログの目的は次の二つだと思います。
1.静岡県東部地方の方々に、五行歌の良さや楽しさを広く知っていただくこと。
2.東部五行歌会の参加者や五行歌に関心をお持ちの方々同士の親睦を深め合うこと。
上記の目的を達成するためには、お互いに五行歌作品を投稿し合ったり、鑑賞コメントを述べ
合ったりすることも必要かもしれません。いずれにしても、楽しく、ホカホカと湯気の立つような
ブログにしていけたら ・・・・ と願っております。
オット、その前に「五行歌っていったいなあに?」という声が聞こえてきそうですね。
それでは、とりあえず、3首ばかりご紹介を・・。
☆
看護婦さんに
笑いかける
私の赤ちゃん
今からちっくん
されるんだよ
陣内洋子
桜の下を
帰ってきたのね
花びら一枚
傘に
のせて
森本いく子
町会の
役員
六十二才で
若手
使い走り
窪谷 登
みなさん、いかがですか?
Posted by 東部五行歌 at
20:58
│Comments(7)
2008年01月18日
静岡県東部五行歌会公式ブログです
昨年5月に発会した
静岡県東部五行歌会です
今や全国規模で 小学生から高齢者まで 盛り上がりをみせている五行歌ですが
もっとたくさんの人に五行歌の楽しさや面白さを知ってもらいたくて
ブログを立ち上げました
メンバーみんなで 五行歌会同様 このブログも盛り上げていきたいと思います
よろしくお願いします
静岡県東部五行歌会です
今や全国規模で 小学生から高齢者まで 盛り上がりをみせている五行歌ですが
もっとたくさんの人に五行歌の楽しさや面白さを知ってもらいたくて
ブログを立ち上げました
メンバーみんなで 五行歌会同様 このブログも盛り上げていきたいと思います

よろしくお願いします